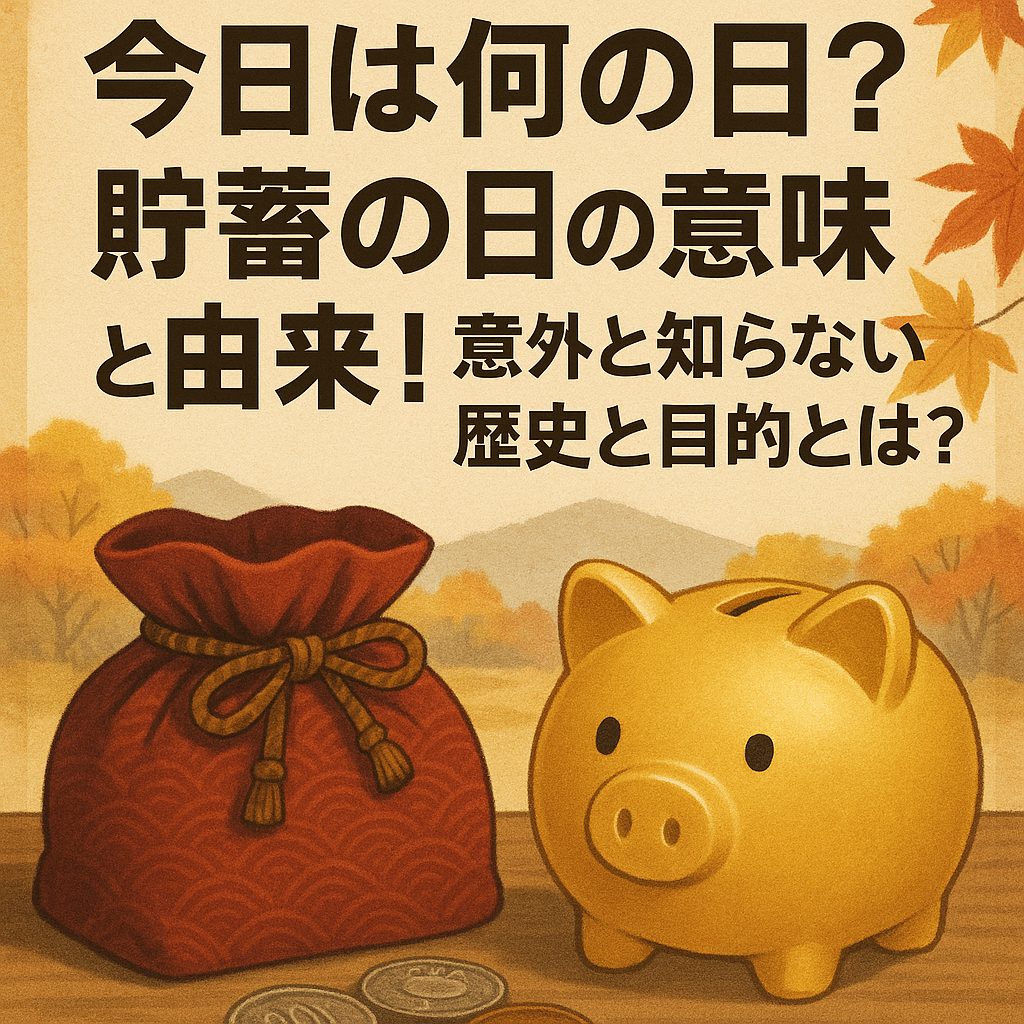10月17日は「貯蓄の日」って知ってましたか?
聞いたことはあっても、「実際にどんな意味があるの?」と感じる人も多いはず。
この記事では、「貯蓄の日」の由来や制定の背景から、今注目されている新NISAやリアルな老後資金事情、都道府県別の貯蓄額まで、気になるお金の話題をわかりやすくまとめました。
読み終えるころには、「よし、私もちょっとだけでも始めてみようかな」って思えるかも。
▼この記事でわかること
・貯蓄の日の意味と由来
・都道府県ごとの貯蓄額ランキング
・老後資金と生活費のリアルな数字
・新NISAの仕組みと活用方法
・今日から始められる節約&貯蓄習慣
今日は何の日?貯蓄の日の意味とは

「貯蓄の日」と聞いて、ピンとくる人は意外と少ないかもしれません。
でも実は、お金の大切さや将来への備えを考える、とっても意味のある記念日なんです。
この見出しでは、貯蓄の日がいつ・どんな理由でできたのかをわかりやすく解説していきます。
そして、今の時代になぜ「貯蓄の日」が注目されているのか、その背景にも触れていきますね。
貯蓄の日はいつ?制定の背景を解説
結論から言うと、貯蓄の日は毎年10月17日です。
この記念日は、1952年に設立された「貯蓄増強中央委員会」(現在は解散)によって制定されました。
その背景には、戦後の日本経済を支えるために、国民全体で貯蓄の重要性を再認識しようという意図があったんです。
10月17日という日付には、実は日本の伝統行事「神嘗祭(かんなめさい)」との関わりがあります。
神嘗祭は、五穀豊穣に感謝する宮中祭祀のひとつ。
そこに込められた「勤労の実り=収入を大切にしよう」という意味が、貯蓄の精神とも重なったんですね。
つまり、「働いて得たお金を無駄にせず、未来のために大切にしよう」という想いが、この日に込められているんです。
次は「神嘗祭」ってなに?という疑問に答えていきますね。
由来は「神嘗祭」!その意味をやさしく紹介
「貯蓄の日」が10月17日なのは、単なる語呂合わせではありません。
実はこの日は、日本の伝統的な祭礼「神嘗祭(かんなめさい)」が行われる日でもあるんです。
神嘗祭は、毎年秋に行われる五穀豊穣を祝う重要な宮中行事で、新米を伊勢神宮に奉納して神に感謝を捧げる儀式です。
この「神への感謝」や「勤労の実り」という意味合いが、貯蓄の大切さとリンクしていることから、「貯蓄の日」の由来になりました。
つまり、お金を「実り」として大切にし、それを守り増やしていくという価値観が根底にあるんですね。
昔から日本では、「稼いだお金をどう使うか」「どれだけ蓄えられるか」を重視する文化があったことがわかります。
この由来を知るだけで、「なんとなく聞いたことある記念日」から、「意味のある日」に感じられますよね。
次は、「今の時代になぜこの日が注目されるのか?」を解説しますね。
なぜ今も「貯蓄の日」が大切なのか?
現代は昔と違って、銀行に預けているだけではお金はほとんど増えません。
それでも「貯蓄の日」が今も大切にされている理由は、お金をただ貯めるだけでなく、自分の未来を守る力を育てる日だからです。
物価はどんどん上がっていて、日々の暮らしもゆとりがないと感じる人が多いですよね。
将来が不安な今こそ、「貯めること=安心につながる」という意識がますます重要になっているんです。
また、最近では貯蓄のスタイルも多様化していて、預金だけでなく投資やつみたて、家計管理アプリなどを使って「賢く守る・増やす」が当たり前になってきました。
そんな時代だからこそ、「貯蓄の日」は家族みんなでお金のことを考えるきっかけになります。
学校や自治体でも、子ども向けにお金の教育イベントが開かれているほど注目されているんですよ。
次の見出しでは、「今の日本人の貯蓄状況」について具体的に見ていきましょう!
貯蓄の日に見る日本人のリアルなお金事情

「貯蓄の日」がある一方で、実際にみんながどれくらい貯めているのか、気になりませんか?
ここでは、都道府県ごとの貯蓄額ランキングや、老後に必要とされる資金の現実、日々の節約習慣について紹介します。
数字を見ることで「自分だけじゃなかったんだ」と安心したり、逆にモチベーションが上がったりしますよ。
一緒に“リアルなお金事情”をのぞいてみましょう。
都道府県別・貯蓄額ランキングで見える格差
ソニー生命が2024年に実施した調査によると、全国の平均貯蓄額にはかなりの地域差があることがわかりました。
なんと**1位は兵庫県(623.5万円)**で、2位は神奈川県(613.8万円)。
都市部や経済圏に属するエリアが上位にランクインしているのが特徴です。
神奈川県は横浜・川崎・相模原といった政令指定都市を持ち、商業活動や企業が集中するため、貯蓄余力のある層が多いと考えられます。
兵庫県については、芦屋市などの高級住宅街が多く、富裕層の存在が平均額を押し上げている要因ともいわれています。
一方で、地方都市になると、貯蓄額の平均は300万円台以下のところも少なくありません。
この結果からわかるのは、住む場所によってお金に対する環境や意識にも差が出るということ。
もちろん、金額だけがすべてではありませんが、自分の地域の立ち位置を知ることで、将来設計のヒントになるかもしれません。
次は、気になる「老後資金」について見ていきましょう!
老後資金はどのくらい必要?シニアの実態とは
「老後資金は2000万円必要」とよく言われますが、実際にはどれくらい貯めている人が多いのでしょうか?
2024年の調査によると、70代の二人以上世帯の貯蓄額は平均1923万円、中央値は800万円でした。
さらに、65歳以上の夫婦世帯に絞ると、平均貯蓄額は2560万円というデータもあります。
数字だけ見ると「意外とみんな貯めてる?」と思うかもしれませんが、注意すべきは貯蓄ゼロの世帯が2割もいるという事実です。
つまり、「しっかり備えてる層」と「全然準備できてない層」に二極化しているんですね。
生活費についても、65歳以上夫婦の平均生活費は月約28.6万円。
この中には食費7.6万円、光熱費2.2万円、医療費1.8万円など、物価高が響く支出が目立ちます。
老後に向けた備えは、「なんとかなる」では通用しにくい時代になってきました。
だからこそ、今のうちから“自分に必要な額”を意識して、無理なく積み立てていく習慣が大切なんです。
次は、そんな「貯める習慣」に注目していきますね!
節約習慣はある?みんなの毎月の貯蓄額をチェック
「貯蓄したいけど、なかなか余裕がない…」そう思っている人も多いですよね。
でも、2025年9月に行われた調査によると、働く20〜50代のうち75.9%の人が何らかの形で貯蓄をしていると回答していました。
毎月の貯蓄額で最も多かったのは「5万円以上〜10万円未満」(18.7%)。
続いて「1万円以上〜3万円未満」(16.3%)、「3万円以上〜5万円未満」(15.2%)と続いています。
つまり、多くの人が「無理のない範囲でコツコツと貯めている」んです。
特に家計簿アプリやスマホでの予算管理、現金チャレンジ、週1ノーマネーデーなど、節約を楽しむ工夫をしている人も増えています。
節約って「我慢するもの」と思いがちですが、今は“生活を整える楽しみ”に変わってきているんですよね。
1日100円でも貯まれば、1年で3万6000円。チリツモの力、あなどれません。
次の見出しでは、「未来に向けた貯蓄方法」として注目されている“新NISA”について解説していきます!
貯蓄の日に始めたい!未来のためのマネー習慣

これまで「貯蓄の日の意味」や「日本人のお金事情」を見てきましたが、やっぱり大事なのは「これからどうするか」ですよね。
このパートでは、今注目の「新NISA」や、初心者でもできる積立投資、そして今日からすぐにできる節約・貯金のコツを紹介します。
どれも難しい話ではなく、生活にちょっと取り入れるだけで未来の安心感につながる習慣ばかりです。
あなたのライフスタイルに合ったマネー習慣を見つけてみてくださいね!
新NISAとは?初心者にもわかる仕組みとメリット
「NISAって聞いたことあるけど、なんだか難しそう…」と思っていませんか?
新NISAは、2024年からスタートした新しい制度で、投資で得た利益に税金がかからないという超お得な仕組みなんです。
普通は、投資で利益が出ると約20%の税金がかかります。
でも新NISAなら、そのまままるっと手元に残せるので、“お金が増えやすい”制度と言えるんです。
主なポイントはこちら👇
-
非課税期間が無期限(ずっと非課税で持てる!)
-
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用できる
-
年間の投資枠は、最大で合計360万円
-
トータル非課税保有限度額は1800万円(再利用もOK)
少額から始められる商品も多くて、月500円〜できる投資信託もありますよ。
「今さら間に合う?」なんて心配はいりません。始めた人から得する制度なので、今日がベストなタイミングです!
次は、新NISAを使った具体的な「積立のシミュレーション」を紹介しますね!
毎月5万円でどれくらい貯まる?積立のシミュレーション
「新NISAで資産形成できるっていうけど、実際いくら増えるの?」
そんな疑問に答えるために、カンタンなシミュレーションを紹介しますね。
たとえば、毎月5万円を15年間、新NISAで積立投資した場合。
利回り(年間の運用益)が3%だと仮定すると、15年後の資産はなんと約1060万円になります。
これは「元本900万円」に対して「約160万円分の利益」が上乗せされたイメージ。
しかもこの利益には税金が一切かからないので、すべてが手元に残るんです。
もちろん、相場によって増減はありますが、長期で積み立てることでリスクは分散され、リターンも安定しやすい傾向があります。
「気づいたら資産が増えていた」って未来、ちょっとワクワクしませんか?
まずは少額からでもOKなので、自分に合った金額で始めてみましょう。
続いて、今日からでもすぐできる節約&貯金アイデアを紹介しますね!
今日からできる!カンタン節約&貯蓄アイデア
「投資はまだちょっとハードルが高いかも…」という人でも、節約や貯蓄ならすぐ始められますよね。
ここでは、今日からできるシンプルだけど効果バツグンのアイデアを紹介します👇
💡手軽に始める節約&貯金術リスト
-
週に1日「ノーマネーデー」を作る
外食やコンビニを我慢するだけでも数千円の節約に! -
おつり貯金アプリを使って自動化
500円貯金がスマホで勝手に積み立てられます。 -
買い物前に“冷蔵庫チェック”を習慣に
ダブり買いや無駄買いを減らせます。 -
1ヶ月の「固定費見直しチャレンジ」
サブスクや保険、使ってないサービスを一度見直してみましょう。 -
100円ノートで“手書き家計簿”
可視化するだけでムダ遣いが減る人も多いです。
これらはどれも、難しいことではなく「少し意識するだけ」でできる習慣ばかり。
しかも、達成感や楽しさがあるから、続けやすいんです。
「貯蓄の日」は、こういった行動を見直す良いきっかけになります。
“未来の自分を助けるのは、今の小さな行動”かもしれませんね。

貯蓄の日に関するよくある疑問Q&A

Q: 貯蓄の日ってどうして10月17日なんですか?
A: 10月17日は「神嘗祭(かんなめさい)」という五穀豊穣を祝う伝統的な祭りの日です。
その日にちなんで、「勤労の実りを大切にしよう」という意味を込めて、1952年に「貯蓄の日」が制定されました。
Q: 日本人ってどれくらい貯金してるんですか?
A: 70代の平均貯蓄額は約1923万円ですが、中央値は800万円と差があります。
また、65歳以上の無職夫婦の生活費は月28万円ほど必要なので、備えが大事ですね。
Q: 新NISAって結局どんな制度なんですか?
A: 新NISAは2024年から始まった「投資で得た利益が非課税になる制度」です。
年間360万円まで投資できて、最長で非課税のまま運用できます。初心者でも少額からスタート可能です。
Q: 毎月どれくらい貯金している人が多いですか?
A: 最も多かったのは「5万〜10万円未満」が約18%。次いで「1〜3万円未満」や「3〜5万円未満」が続きました。
少額でもコツコツ積み立てる人が多い傾向にあります。
Q: 今日からできる節約術には何がありますか?
A: ノーマネーデーを設ける、アプリで自動貯金、家計簿で見える化などがおすすめです。
小さな習慣を続けることが将来の安心につながりますよ。
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました。以下に要点をまとめます。
-
10月17日は「貯蓄の日」。由来は神嘗祭で「働くことの実りを大切に」という意味がある
-
貯蓄額の都道府県ランキングでは兵庫県や神奈川県が上位
-
70代や65歳以上の生活費や老後資金のリアルデータも公開
-
毎月の平均貯蓄額は5万〜10万円が最多。75%以上の人が何らかの貯蓄をしている
-
新NISAを活用すれば、税金がかからず資産形成が可能
-
ノーマネーデーやアプリでの積立など、誰でも始められる節約習慣も多数紹介
貯蓄の日は、「お金のことを考えるきっかけ」としてぴったりの日です。
将来に備えて、無理なく・楽しく続けられる習慣を見つけてみてくださいね!