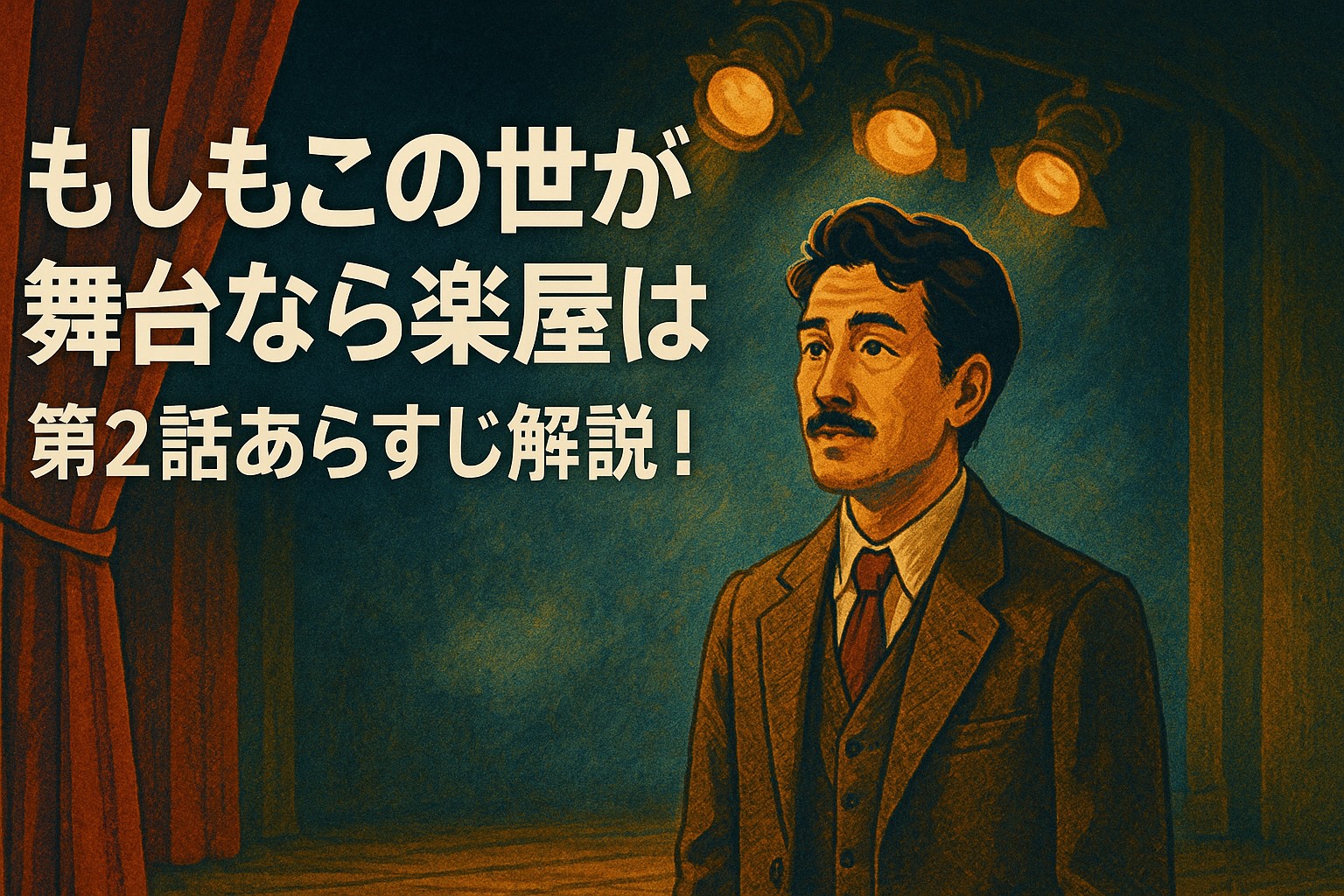2025年秋ドラマの中でも、ひときわ異彩を放つ作品『もしもこの世が舞台なら楽屋はどこ』。
第2話では、渋谷の小さな劇場を舞台に、夢と現実のはざまで揺れる若者たちのリアルな人間模様が描かれました。
菅田将暉・神木隆之介・二階堂ふみら豪華キャストが演じるキャラクターたちは、まるで自分自身を映し出す鏡のよう。
この記事では、第2話のあらすじや見どころ、登場人物の関係性、主題歌「劇上」に込められた意味まで、徹底的に解説します。
視聴後のモヤモヤや感動を、この記事でぜひ整理してみてください。
もしもこの世が舞台なら楽屋はどこ 第2話あらすじ解説!
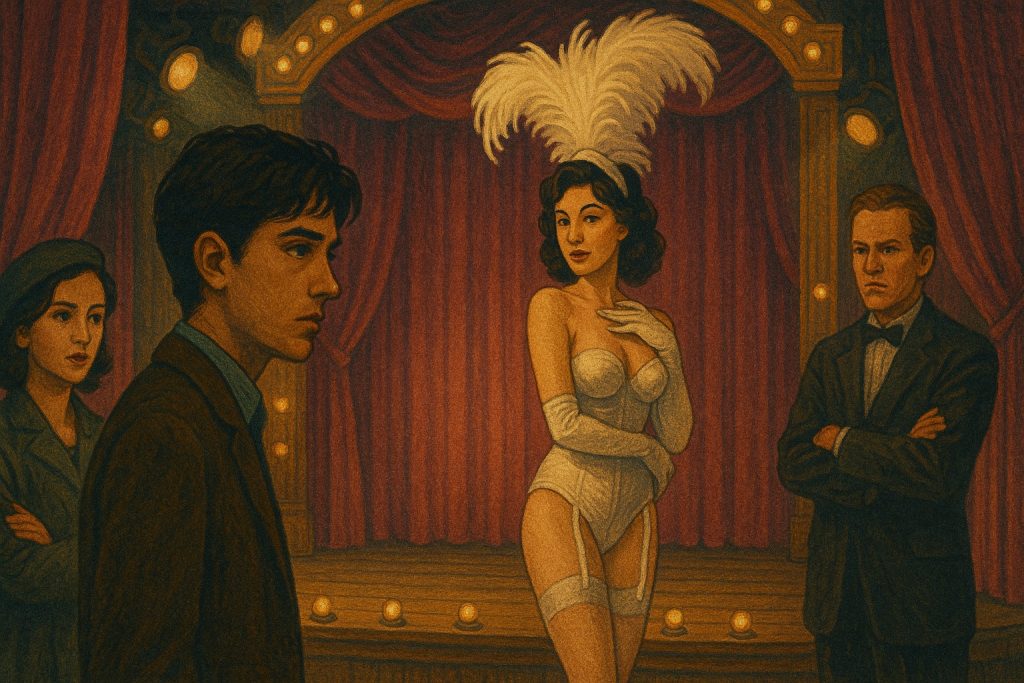
昭和の渋谷を舞台に展開する青春ドラマ「もしがく」の第2話では、主人公・久部三成とリカの再会が描かれ、大きな注目を集めました。
今回はその見どころとストーリーを、分かりやすく丁寧に解説していきますね。
舞台は1984年の渋谷・WS劇場
1984年の渋谷に実在したかのようなWS劇場が、物語の舞台です。
かつてはにぎわっていたストリップ劇場も、風営法の改正によって閑散とした雰囲気に変わってしまいました。
主人公の久部三成(菅田将暉)は、劇場の支配人からの誘いでここで働くことに決め、ピンスポットを担当します。
劇場の奥深く、照明が灯るその裏で、若者たちの人生の火花が静かに、でも確かに燃え上がっていきます。
昭和の熱気と、静まりゆく現場の対比がとても印象的な導入です。
次は、そんな劇場で久部が再会を果たすことになる“リカ”との関係に注目していきます。
久部とリカの再会シーンに注目
第2話の最大の見どころのひとつが、久部三成(菅田将暉)とリカ(二階堂ふみ)の再会シーンです。
久部は劇場スタッフに導かれて、ダンサーたちの楽屋に挨拶へ向かいます。そこで出会ったのが、以前交流のあったリカ。
「頑張ります!」と意気込む久部の言葉に、リカは冷たく目をそらします。
この一瞬のやり取りが、2人の過去と現在の距離を物語っていて、すごくリアルなんですよね。
久部はまだ夢を追いかけていて、リカはすでにどこか“諦め”のようなものを身にまとっている。
そんな対照的な2人がまた同じ空間で交差することで、今後の物語にどう影響していくのか、視聴者の興味を引きつける構成になっています。
次は、2人を取り巻く「ストリップショー」と「演劇」の対比に注目していきましょう。
ストリップショーの現実と演劇のはざまで
第2話では、ストリップショーという表舞台と、演劇という夢の舞台の間に揺れる登場人物たちのリアルが描かれます。
WS劇場で踊るパトラ(アンミカ)は、かつて熱狂を呼んだスターですが、今や観客の少なさにため息をつく日々。
そのステージの裏側で、久部三成は照明係として参加しながら、自分の夢と現実のギャップに気づき始めます。
煌びやかに見える“舞台”の裏側には、努力とあきらめ、期待と不安が交錯している。
まさにこのドラマが伝えたい「舞台」と「楽屋」のメタファーが、物語の至るところに仕込まれていて、見れば見るほど味わい深くなるんです。
第2話ではその“はざま”で生きる人たちの葛藤が丁寧に描かれ、視聴者の胸にも静かに響いてきます。
次は、現代の視聴者にグッと刺さるもう一つの見どころ、「渋谷の片隅で生きる若者たちのリアル」について掘り下げていきます。
渋谷の片隅で生きる若者たちのリアルとは?

第2話では、ただの“懐かしの昭和描写”では終わらない、登場人物たちの生々しい葛藤と希望が描かれています。
ここでは、菅田将暉・神木隆之介・二階堂ふみが演じる若者たちの姿を通して、今の視聴者に響く“リアル”を読み解いていきましょう。
菅田将暉が演じる久部三成の葛藤
第2話で描かれる久部三成(菅田将暉)は、“夢を追いかける若者”というシンプルな像にとどまりません。
演出家になるという目標はあるけれど、何者でもない自分を前に、焦りと不安が渦巻いているのがわかります。
WS劇場の現実を見て、かつて憧れていた舞台の世界が、こんなにも寂れているというギャップにも苦しむ姿が印象的です。
そんな中でも「頑張ります!」と空回り気味に気合いを入れる久部の姿は、視聴者の誰もが過去に感じた“がむしゃら”な自分と重なる瞬間。
菅田将暉の繊細な演技が、久部の揺れる心をリアルに描き出していて、見ているこちらの胸にもジンと響いてきます。
次は、久部を見守る立場でもあり、ちょっとしたキーパーソンでもある蓬莱省吾に注目してみましょう。
神木隆之介演じる蓬莱省吾の役割とは?
神木隆之介が演じる蓬莱省吾は、ドラマの中で一見すると脇役のように見えますが、実はとても重要な役割を担っています。
蓬莱は若き日の三谷幸喜をモデルにしたキャラクターで、新人放送作家としてストーリーの外側から世界を見ているような存在です。
熱量が空回りする久部とは対照的に、蓬莱は一歩引いた目線で冷静に物事を観察しています。
でもその分、蓬莱自身も何かに踏み出す勇気を持てずにいるようにも見えて、そこがまた人間らしくて惹かれるんですよね。
久部と蓬莱の距離感や、会話の中にあるちょっとしたズレが、物語に奥行きを加えています。
今後、この2人の関係性がどう変化していくのかも、見逃せないポイントです。
次は、久部とも蓬莱とも違う、“リカ”という存在に注目していきましょう。
二階堂ふみ=リカが象徴する“夢と現実”
二階堂ふみが演じるリカは、第2話において“夢を持つことの残酷さ”と“現実を生きる強さ”の両方を体現している存在です。
かつて久部と何らかの関係があったことが仄めかされるものの、再会したリカはすでに別人のように冷めた視線を持っています。
ストリップ劇場で働く彼女に、かつての夢や理想が残っているのかどうか——それすらも分からないまま、日常を淡々とこなしている姿がとてもリアル。
「頑張ります」という久部の言葉に、目をそらすあの一瞬。
あの無言のリアクションに込められたものは、きっと“もう何も期待していない”という決意と、“それでもどこかで期待してしまう自分”の葛藤なのかもしれません。
リカは、夢を諦めきれずにいる視聴者の心に、グサッと突き刺さる存在です。
次は、こうしたキャラクターたちの物語を通して、三谷幸喜が描こうとしている“舞台と楽屋”の本質に迫っていきます。
三谷幸喜の世界観に込められたメッセージ

「もしもこの世が舞台なら楽屋はどこ」というタイトル自体がすでに象徴的ですが、第2話ではその“問い”に対するヒントのようなものが随所に散りばめられています。
ここでは、三谷幸喜がこの作品を通して伝えたい深層メッセージに迫っていきましょう。
青春群像劇に見える“楽屋”の意味とは?
三谷幸喜が描く「もしがく」は、単なる青春ドラマではなく、「舞台=表の人生」「楽屋=本音や孤独」といったメタファーが巧みに仕込まれています。
特に第2話では、表では明るく振る舞う登場人物たちが、裏では悩みや迷いを抱えている様子が丁寧に描かれます。
久部の“頑張ります”という言葉も、舞台では力強く聞こえますが、楽屋では空元気に近いような脆さが見え隠れしています。
リカやパトラも、舞台上ではプロフェッショナルな振る舞いを見せる一方、舞台裏ではため息や本音がこぼれる。
この“二面性”を浮き彫りにすることで、三谷は「人間は誰もが二つの顔を持って生きている」という普遍的な真理を投げかけているように感じられます。
次は、そんな物語の構造に宿る、三谷幸喜自身の人生とのリンクに迫ってみましょう。
脚本に込められた三谷幸喜の半自伝的要素
実は本作には、脚本家・三谷幸喜自身の若き日が色濃く反映されていると言われています。
特に、第2話から登場した蓬莱省吾(神木隆之介)は、三谷本人をモデルにしたキャラクターとして描かれており、放送作家志望で台本を必死に書いている姿がリアルです。
そのリアリティは、実体験をもとにしたからこその“生々しさ”があり、だからこそ視聴者に刺さるんですね。
また、1984年の渋谷という舞台設定も、三谷が実際に過ごした青春時代と重なります。
当時の空気感や、夢を持つことの切なさ、不器用な人間関係などが、ドラマの随所に染み込んでいるのが感じられます。
こうした“私小説”的な要素が、物語に深みとリアルを与えているのです。
次は、そんな“昭和”の価値観が、令和を生きる私たちにどう響いているのか?を考察していきます。
昭和と令和の価値観がぶつかる舞台設定
第2話で描かれる1984年の渋谷は、現代の視聴者から見るとまるで別世界のように感じられるかもしれません。
当時の風営法や劇場文化、ストリップショーの存在などは、令和ではなかなかリアルに想像できない文化背景です。
しかしその舞台の中で語られる“夢を追う苦しさ”や“人との距離感”は、時代を超えて共感を呼びます。
久部やリカ、蓬莱たちが抱える悩みや焦りは、現代の若者たちがSNSや将来への不安を感じるのと本質的には同じ。
昭和という“古い価値観”の中に、今の私たちが生きる“現代の孤独”や“もどかしさ”を見出せるのが、このドラマの大きな魅力です。
だからこそ、「もしがく」は、単なるレトロドラマではなく、むしろ“今を生きるためのヒント”をくれる物語なのかもしれません。
次は、そんな物語を音楽でさらに深化させている、YOASOBIの主題歌「劇上」に注目していきます。
YOASOBIの主題歌「劇上」が示す物語の伏線

物語を締めくくるエンディングに流れるYOASOBIの「劇上」は、ドラマ全体のテーマを見事に補完する存在です。
この章では、歌詞の意味や映像とのリンクに注目しながら、“音楽”という視点から物語を深読みしてみましょう。
「劇上」に込められた歌詞の意味を考察
YOASOBIの「劇上」は、ドラマの世界観に深く寄り添った主題歌として話題を集めています。
この曲は三谷幸喜が書き下ろした小説『なにしてるのかわからないけど、何かをしてる』を原作にしており、まさにドラマの“もうひとつの脚本”とも言える存在。
歌詞には「舞台の上に立つ意味」「自分らしく生きる難しさ」「不完全なまま進むこと」など、物語とリンクするテーマが丁寧に込められています。
特に「誰の声でもない声を信じて進め」という一節は、第2話で久部やリカが感じていた“迷いの中の決意”を象徴しているかのようです。
YOASOBIらしい繊細なメロディと物語性の強い歌詞が、視聴者の感情を優しく包み込んでくれます。
次は、この主題歌がどのように物語と映像に結びついているのかを見ていきましょう。
物語と楽曲のリンクに視聴者は何を感じた?
YOASOBIの「劇上」は、単なるエンディングテーマではなく、物語の余韻を深める“第2のナレーション”のような存在です。
第2話のラスト、久部の少し前向きな表情とともに流れる「劇上」のサビは、視聴者に「まだ物語は終わっていない」と感じさせてくれます。
SNS上では「歌詞を見て涙が出た」「まるで久部の心の声みたい」といった感想も多数寄せられており、歌とドラマのシンクロに多くの共感が集まりました。
また、YOASOBI特有のストーリー性を持つ楽曲だからこそ、登場人物たちの感情や背景を想像しやすくなり、ドラマの世界観がより一層立体的に感じられます。
まさに、音楽がドラマの感情線を“補完”するだけでなく、“深化”させている好例です。
次は、そんな「劇上」の中でも特に象徴的なシーン——“幕が上がる瞬間”について、最後に掘り下げていきましょう。
YOASOBIが描く“幕が上がる”瞬間のエモさ
YOASOBIの「劇上」の中で特に印象的なのが、“幕が上がる”という象徴的なモチーフです。
これはまさに、久部たちが自分の人生に踏み出していくその瞬間を表しているように感じられます。
第2話のラストでは、久部が少しずつ劇場の仕事に慣れ、仲間たちと微笑み合うシーンが描かれます。
その直後に流れる「劇上」の歌詞と重なることで、彼の中で何かが動き始めた——そんな“始まりの予感”が静かに胸を打つんです。
YOASOBIが得意とする「音楽で物語を締めくくる」力が、このドラマでも存分に発揮されており、視聴者の余韻を深めています。
その“幕が上がる”瞬間こそが、視聴者にとっても新たな共感や気づきを与えてくれるのです。
よくある質問(Q&A)

Q: 第2話の舞台「WS劇場」は実在する場所ですか?
A: 実在はしませんが、1980年代の渋谷に実在したようなストリップ劇場をモデルにした、非常にリアルな舞台設定です。昭和の空気感を再現するための象徴的な場所として描かれています。
Q: 久部とリカは過去にどんな関係だったのでしょうか?
A: 明確には描かれていませんが、過去に親しい関係にあったことが仄めかされています。第2話の再会シーンでは、リカが久部の視線を避ける描写があり、2人の間に何かしらの因縁があることが感じ取れます。
Q: 蓬莱省吾のキャラクターにはどんな意味がありますか?
A: 蓬莱は、三谷幸喜の若き日の姿を投影したキャラクターです。夢を持ちながらも客観的な視点を持つ彼は、物語の“語り手”としての役割も担っており、物語のもう一つの軸を示しています。
Q: YOASOBIの「劇上」はどんな視点で書かれているのですか?
A: 「劇上」は三谷幸喜の原作小説をもとに書かれた楽曲で、登場人物たちの葛藤や希望を優しく包み込むような歌詞が特徴です。舞台に立つ人の視点をベースにしながら、聴く人自身の物語にも寄り添う内容になっています。
Q: ドラマのテーマ「楽屋」はどういう意味を持っているのですか?
A: 楽屋は“本音”や“素顔”の象徴として描かれています。舞台が「人に見せる人生」なら、楽屋は「誰にも見せない人生の裏側」。登場人物たちの葛藤や迷いが見える場面こそが、“楽屋”の本質を表しています。
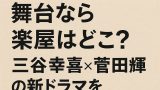
まとめ
今回の記事では、ドラマ『もしもこの世が舞台なら楽屋はどこ』第2話について、以下のポイントを解説しました。
-
菅田将暉演じる久部とリカの再会が切ない
-
ストリップショーの現場が舞台と楽屋のメタファーに
-
三谷幸喜の自伝的要素が色濃く反映された脚本構成
-
昭和と令和の価値観が交錯する奥深い世界観
-
YOASOBI「劇上」が物語の感情を包み込むように響く
第2話は、ただの昭和レトロな物語ではなく、現代を生きる私たちに問いかける深いテーマが込められていました。
誰にも見せない“楽屋”の顔と、見せなければいけない“舞台”の顔。その狭間で揺れる人間模様が丁寧に描かれた回でしたね。
この記事を通して、少しでも作品の世界を深く味わうきっかけになっていたら嬉しいです。
次回の展開も見逃せません!