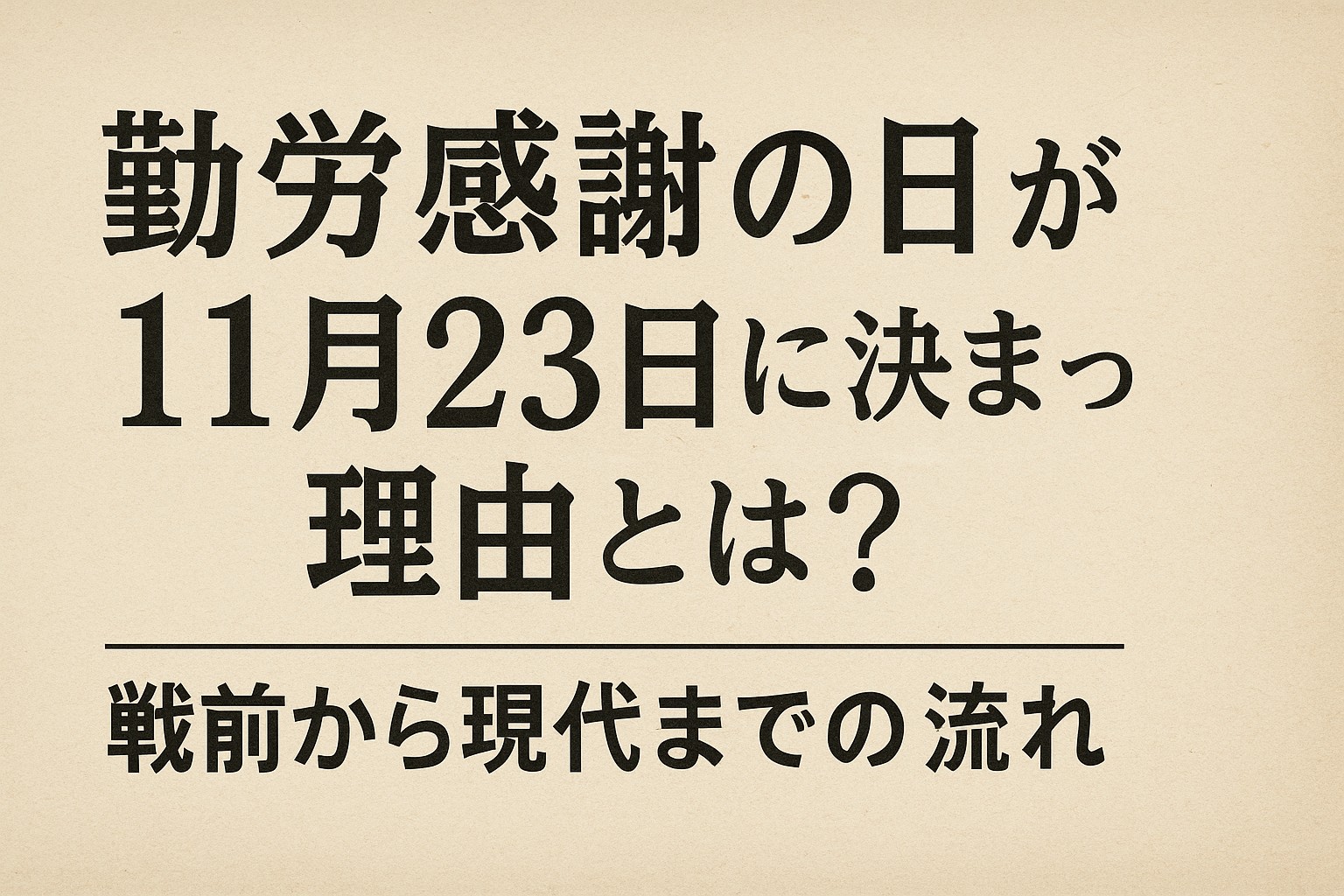「勤労感謝の日って、どうして11月23日なの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?
毎年決まってこの日に休みがあるのは、実は日本の古くからの伝統や戦後の制度改正が関係しているんです。
この記事では、勤労感謝の日の由来や意味、海外との違い、そして家族での過ごし方までを、わかりやすく解説します。
子どもにも伝えたくなる「感謝の文化」を一緒に深めていきましょう!
勤労感謝の日が11月23日に決まった理由とは?

勤労感謝の日が毎年11月23日なのは、実は古くからの伝統行事「新嘗祭(にいなめさい)」に由来しています。
現代では労働への感謝の日とされていますが、その背景には戦前から続く祭事と、戦後に制定された祝日法の影響があるのです。
この章では、その歴史の流れをたどりながら、なぜ11月23日という日付が変わらず続いているのかを紐解いていきます。
次の見出しでは、まず「新嘗祭」との関係から解説していきましょう。
元々は「新嘗祭」だった?その由来とは
勤労感謝の日のルーツは、古来から日本で行われていた「新嘗祭(にいなめさい)」という宮中行事にあります。
これは、毎年11月23日に、天皇が五穀豊穣を神々に感謝し、新米を食する儀式です。
農耕民族である日本人にとって、五穀豊穣への感謝は非常に大きな意味を持っていました。
そのため、長くこの日は国民的な節目の日とされてきたのです。
現代の勤労感謝の日は、この新嘗祭をベースにして形を変えたものといえます。
続いて、戦後にこの祝日がどのように変化したのか見ていきましょう。
戦後の祝日法でどう変わったのか
戦後、日本はGHQの占領下に置かれました。
その中で、国家神道との関係を断ち切るために、宮中行事に由来する祝日の見直しが行われたのです。
1948年、「国民の祝日に関する法律(祝日法)」が施行され、新嘗祭は「勤労感謝の日」と名前を変えて祝日として存続することになります。
ただし、儀式的・宗教的な意味合いを排除し、「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日」として定義されました。
つまり、表面的には新しい意味が与えられつつも、日付はそのまま引き継がれたのです。
それでは、なぜ11月23日という日付が変わらず続いているのでしょうか?
なぜ今も11月23日なのか?
祝日の見直しがあったにもかかわらず、11月23日が維持されたのにはいくつかの理由があります。
まず、国民の生活リズムや農業・収穫文化と結びついていたため、他の日に変更するのは困難だった点。
さらに、新嘗祭という文化的・歴史的な重要性を背景に、日付のみは踏襲する形となったと考えられます。
また、戦後は経済復興の真っただ中。
「働くこと」「生産すること」への感謝を祝日にすることで、国民の士気を高めるという政治的な意図もあったのです。
こうして11月23日は、形を変えながらも「感謝の心を育てる日」として現代まで続いています。
次の章では、勤労感謝の日が持つ「意味」と「役割」について、より具体的に見ていきましょう。
勤労感謝の日の意味と役割

勤労感謝の日は、単に「仕事をしている人にありがとうを伝える日」というだけではありません。
法律や文化の背景をふまえると、この祝日はもっと深く、私たちの日常生活や社会の在り方を映し出す記念日でもあるのです。
この章では、「勤労」という言葉の意味や、この祝日をどう捉えるべきかについて、子どもにもわかりやすく説明していきます。
まずは「感謝する対象」が誰なのかを整理してみましょう。
「勤労に感謝する」とはどういうこと?
「勤労に感謝する」とは、日々働いている人々すべてに対して、「ありがとう」を伝えることです。
会社員や公務員、医療従事者だけでなく、農業・漁業・物流・清掃など、社会を支えるすべての仕事に感謝の気持ちを持つ日とされています。
また、主婦や家事をしている人、自営業の人、学校で勉強する子どもたちも含めて、「自分の役割を果たすこと=勤労」と捉えることができます。
感謝する相手は、他人だけではありません。
「今日もがんばった自分自身」への感謝も含まれるのです。
では、こうした考えを子どもにどう伝えたら良いのでしょうか?
子どもにもわかる!感謝の気持ちを伝える日
勤労感謝の日は、子どもたちにとって「人は支え合って生きている」ということを知るチャンスです。
例えば「毎日ごはんを作ってくれるおうちの人にありがとうを言う」「学校の先生にお手紙を書く」「地域で働く人にあいさつをする」など、身近な行動から感謝を学ぶことができます。
幼稚園や小学校では、この日に合わせて「お仕事体験」や「感謝のお手紙作り」などの行事を行うことも多いです。
こうした取り組みは、「働く=大変」ではなく「誰かの役に立っている」という実感を持つきっかけになります。
最後に、実際に感謝を伝えるにはどんな方法があるのかを見てみましょう。
仕事をする人たちにどう感謝を伝える?
感謝の伝え方は、必ずしも大げさである必要はありません。
「ありがとう」と一言伝えるだけでも、相手にとっては大きな励みになります。
家族や友人、職場の同僚に感謝の言葉をかけるのもよいですし、SNSで自分の想いを発信するのも一つの手です。
また、地元のスーパーや駅員さん、郵便配達員さんなど、日頃目にする「縁の下の力持ち」に向けて、感謝の手紙や小さな贈り物を用意するのも素敵な取り組みです。
「感謝の気持ち」は見えないけれど、行動にすることで伝わるもの。
この日をきっかけに、感謝の習慣を日常に広げていけると良いですね。
次は、勤労感謝の日と似たような「感謝の祝日」が、海外ではどうなっているのかを見ていきましょう。
海外の「感謝の日」との違いは?
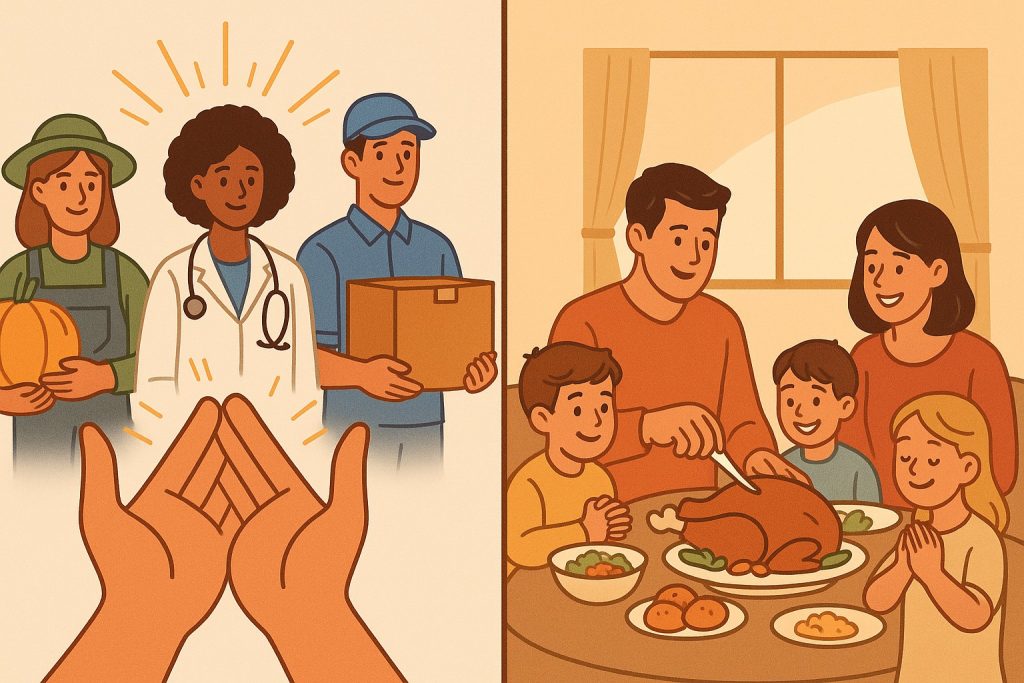
勤労感謝の日は日本独自の祝日ですが、海外にも「感謝」にまつわる祝日が存在します。
特に有名なのが、アメリカの「サンクスギビング・デー(感謝祭)」です。
日本の勤労感謝の日とどう違うのでしょうか?
また、他の国々では「労働」に関連した祝日がどのように設定されているのでしょうか。
世界との違いを知ることで、日本の勤労感謝の日の意味がさらに深まります。
アメリカのサンクスギビングとどう違う?
アメリカの「感謝祭(Thanksgiving Day)」は、11月の第4木曜日に祝われます。
由来は、17世紀に移住した清教徒(ピルグリム・ファーザーズ)が初めての収穫を祝ったことに始まるとされ、家族で七面鳥などのごちそうを囲むのが一般的です。
この日は「神への感謝」「収穫への感謝」「家族との団らん」がキーワードで、宗教的・歴史的背景が濃い点が特徴です。
一方で、日本の勤労感謝の日は宗教色が薄く、「働くこと」に対する感謝がメインテーマ。
アメリカのサンクスギビングが「収穫と神に感謝する日」ならば、日本は「人の労働と努力に感謝する日」といえます。
各国の労働に関する祝日事情
世界には「労働」に関連する祝日が多く存在します。
代表的なのが「メーデー(May Day)」です。
これは5月1日に行われる国際的な労働者の祝日で、ヨーロッパ諸国を中心に広く祝われています。
フランスやドイツ、イタリアなどでは、労働者の権利や社会的な平等を訴える日として、デモやパレードが行われることもあります。
一方、日本ではメーデーは祝日ではなく、「勤労感謝の日」がその役割を担っているといえるでしょう。
日本独自の形で「労働」への敬意を表す日が制定されているのは、ある意味で国民性を反映しているのかもしれません。
では、そんな勤労感謝の日を家庭でどう過ごせば、意味のある1日になるのでしょうか?
勤労感謝の日を家族でどう過ごす?
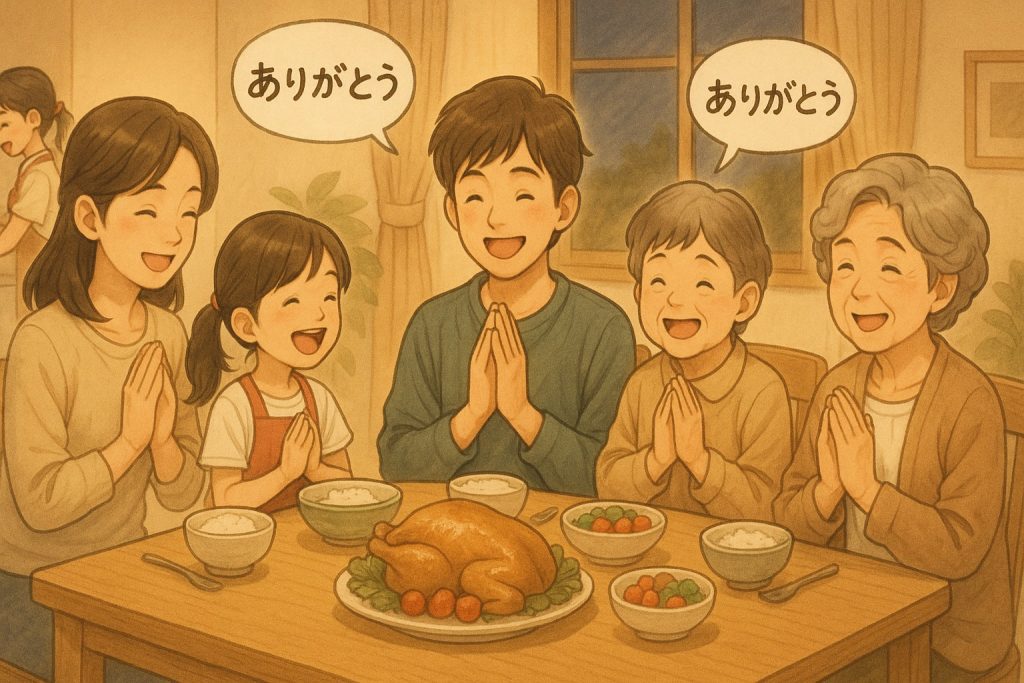
勤労感謝の日は、単なる「お休み」ではなく、家族の中で感謝の気持ちを伝え合う大切な機会です。
忙しい毎日の中で、改めて「ありがとう」と言葉にするだけで、家庭の雰囲気はぐっと明るくなります。
ここでは、子どもと一緒に楽しみながら感謝の心を育むためのアイデアをご紹介します。
子どもと一緒にできる感謝のアクション
小さな子どもにも伝わる「感謝のアクション」は意外とシンプル。
たとえば「お父さんにお手紙を書こう」「お母さんの好きな料理を一緒に作ってあげよう」など、日常の延長にあるもので構いません。
「今日は誰にありがとうを伝えたい?」と問いかけてみるだけでも、子ども自身が「感謝」を考えるきっかけになります。
また、保育園や小学校でも、似たような活動が取り入れられることが多く、子どもにとっては身近な祝日となってきています。
家庭での小さな習慣が、大人になっても心に残る大切な記憶になるかもしれません。
学校や職場で取り入れたいアイデア
学校や職場でも、勤労感謝の日にちなんだ取り組みを行うことで、感謝の気持ちを共有することができます。
学校では、地域の郵便局員さんやバスの運転手さんにお礼の手紙を送るといった「ありがとうプロジェクト」が実施されることも。
職場では、「いつもありがとうカード」を配る、昼休みに感謝の一言を共有するなど、形式にこだわらず柔らかな雰囲気づくりが効果的です。
大切なのは、感謝を「伝えよう」と思うその気持ち。
勤労感謝の日は、そうした一歩を踏み出すきっかけになるのです。
勤労感謝の日に関するQ&A

Q: 勤労感謝の日が11月23日になった理由は何ですか?
A: 古来の収穫感謝行事「新嘗祭」が11月23日に行われていたことに由来します。戦後、宗教色を排除して「勤労感謝の日」として祝日化されましたが、日付はそのまま残されました。
Q: 勤労感謝の日とアメリカのサンクスギビング・デーの違いは?
A: サンクスギビングは「収穫と神への感謝」が中心で、家族団らんの日です。一方、日本の勤労感謝の日は「働く人への感謝」が主旨で、宗教色はありません。
Q: 子どもに勤労感謝の日の意味をどう伝えれば良い?
A: 身近な人への「ありがとう」を考えさせるのが効果的です。例えば「ごはんを作ってくれる人」や「働いている家族」に感謝の手紙を書くなどのアクションを通じて学べます。
Q: 勤労感謝の日は世界でも祝われているの?
A: 日本独自の祝日ですが、世界には「労働者の権利」に関する祝日(例:メーデー)が多く存在します。形や日付は異なりますが、働くことを尊ぶ文化は各国にあります。
Q: 勤労感謝の日に家庭でできる過ごし方はありますか?
A: 子どもと一緒にお手紙を書いたり、家事を手伝ったり、小さな感謝を「行動」にするのがおすすめです。職場では感謝カードを配る取り組みも人気です。
まとめ
今回の記事では、勤労感謝の日がなぜ11月23日なのか、その由来や意味、海外との違いまでを解説しました。
以下に要点をまとめます。
-
勤労感謝の日は、古来の「新嘗祭」に由来する
-
1948年の祝日法により「勤労感謝の日」として制定された
-
日付が変わらなかったのは、文化的・季節的な背景があるから
-
アメリカのサンクスギビングとは由来も意味も異なる
-
子どもと一緒に「ありがとう」を伝える行動が大切
11月23日は、単なる休日ではなく「働くことの大切さ」と「感謝する心」を再認識する日。
この日をきっかけに、日常の中でも小さな「ありがとう」を伝える習慣を作ってみませんか?